出産のママさん達のお話からも、旦那さんが妊娠中にどれだけ気遣ってくれたか、ご家庭によってまちまちね~
ひとことで良いから声がけしてもらいたかったという不満も多いみたいだよ。
妊娠・出産における夫婦のトラブルは旦那さんが事前に妊娠に対する知識を入れておき、奥さんを気遣う行動することよって避けることができます。
夫婦不和を招かないように、特に旦那さんに読んで欲しい記事となっています。
現役専門医が推奨する内容ですので、旦那さんに直接読んでもらえると良いですよ♪
目次
妊娠・出産における夫婦のトラブルランキング
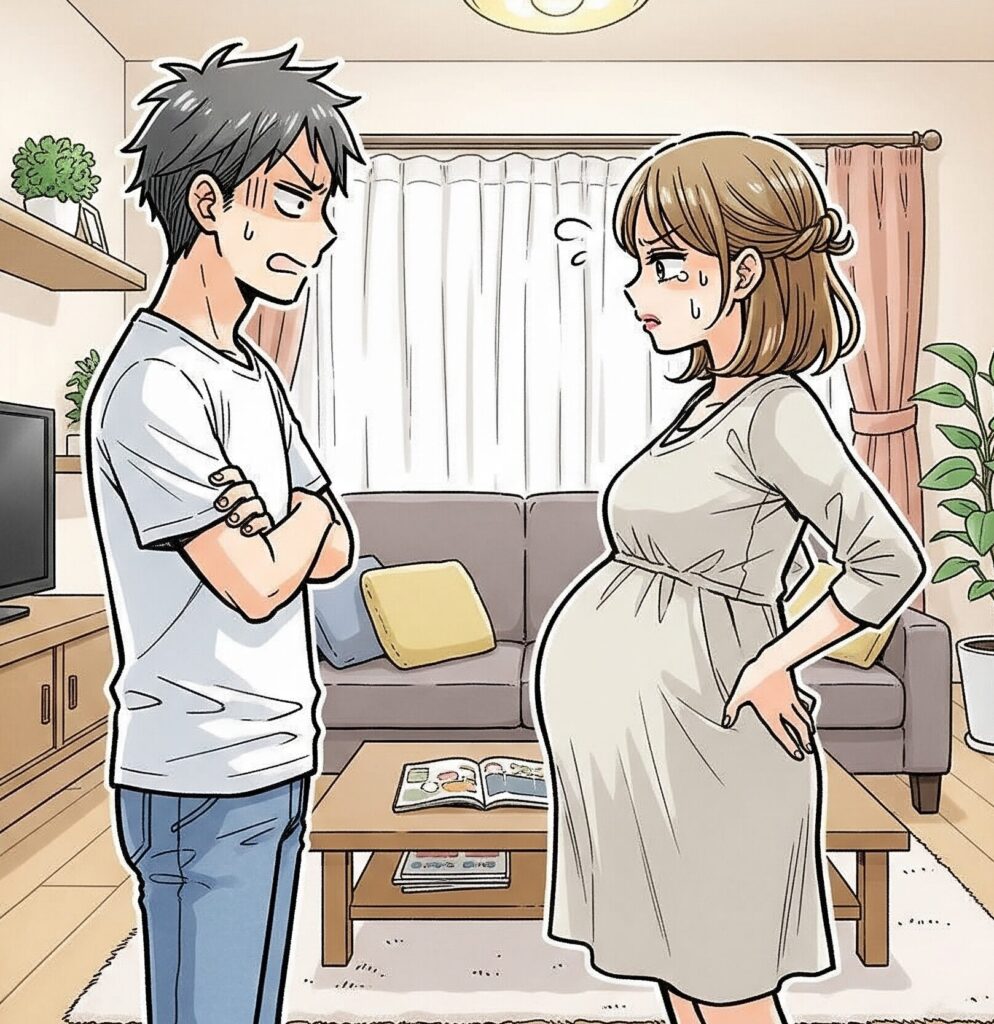
なぜ、奥さんが妊娠したら旦那さんの神対応が求められるか、まずは夫婦が妊娠・出産で経験する主なトラブルをランキング形式で紹介します。
奥さんの不満が積もり積もって離婚危機が発生しないように、旦那さんの事前の神対応が大切ね。
1位:つわりや体調不良への理解不足
妊娠初期のつわりの辛さや、妊娠中の体調変化に対する夫の理解不足が最も多い問題です。「大げさ」「甘え」と捉えられることで夫婦関係に亀裂が生じるケースが多数報告されています。
2位:家事・育児分担の偏り
妊娠中から産後にかけて、家事や育児の負担が妻に集中し、夫の協力が得られないことによる不満やストレスが深刻化するケースです。
3位:経済的な不安と価値観の違い
出産費用、育児用品、今後の教育費などに対する経済観念や優先順位の違いが原因となる対立です。
4位:両親・義両親との関係悪化
妊娠・出産を機に、双方の両親からの過干渉や価値観の押し付けが原因で夫婦間に緊張が生まれるケースです。
5位:夫の生活習慣の変化への対応不足
妊娠中の妻に合わせた生活リズムの調整や、禁酒・禁煙への協力不足による摩擦です。
6位:産後うつ・育児ノイローゼへの無理解
産後の精神的不安定さやホルモンバランスの変化に対する夫の理解不足が問題となるケースです。
7位:性生活に関する認識の違い
妊娠中や産後の性生活について、安全性や再開時期に関する認識の違いから生じる問題です。
8位:育児方針の食い違い
しつけ方法、教育方針、子どもとの接し方について夫婦間で意見が対立するケースです。
9位:睡眠不足による精神的余裕の欠如
新生児の夜泣きや授乳による睡眠不足で、些細なことでも衝突しやすくなる状況です。
10位:職場復帰や働き方に関する意見の相違
妻の職場復帰のタイミングや働き方について、夫婦間で考えが一致しないケースです。
このランキングからもわかるように、夫婦円満は奥さんの妊娠中、どれだけ相手を気遣った言動ができるかにかかっているのです。
神対応1.積極的な家事分担

(30代女性、妊娠初期の声) 「つわりで動けないとき、料理や掃除を率先してやってほしかった。『言ってくれればやるよ』じゃなくて、自分から気づいて動いてほしかった。」
多くの妊婦さんが、旦那さんが自発的に家事を引き受けてくれることを期待していました。
特に、妊娠中の疲れや体調不良で家事が負担になる時期に、言わなくても動いてほしかったという声が目立ちます。
妊娠中に旦那さんが積極的に家事を分担する方法について、具体的なポイントや実践のコツをまとめます。
- 家事リストを一緒に作る
料理・掃除・洗濯・ごみ捨てなど、日々の家事項目を紙やアプリで見える化し、どれを誰が担当するか話し合って決めると、分担が明確になりやすいです。 - 担当家事を丸ごと任せる
一部だけをやるのではなく、例えば「料理は買い物・献立決め・調理・後片付けまで全部担当する」など、一連の流れごと夫に任せることで、負担軽減につながります。 - 妊娠中に特につらい家事を率先して行う
重い物を持つごみ捨てや買い物、お風呂掃除、布団の上げ下ろし、食器洗い、掃除機がけなど、体に負担のかかる作業は特に旦那さんが積極的に担当しましょう。 - 目に付きにくい「名もなき家事」も気づいて実践する
消耗品の補充やゴミ袋のセット、玄関や水回りの整理、郵便物のチェックなど、細かい作業も意識して引き受けると、パートナーの負担が大きく軽減されます。 - 時短家電・家事代行サービスの活用も検討
料理や掃除などの負担を減らすため、ロボット掃除機や食洗機、家事代行サービスの利用も前向きに取り入れるのがおすすめです。 - 話し合いを重ねて柔軟に調整する
体調や気分によって分担は変わるもの。定期的に「今つらい家事は何か」「できること・できないこと」を夫婦でコミュニケーションしながら見直しましょう。
家事分担で実際に役立った工夫やコツの例
- 「自発的にやる」「やって当たり前と思わず感謝を伝える」という気持ちが大切という声が多く聞かれています。
- 紙にやることを書き出して、一目で分かるようにしたり、日によって交代する方法も有効です。
- 名もなき家事も含めて“気づいた方がやる”ルールにする、という体験談もあります。
妊娠中は体調や気分の変化が激しい時期なので、分担の割合や内容は家庭ごとに最適解が異なります。お互いの希望をこまめに確認しあいながら協力して進めていきましょう。
神対応2.妻の体調変化に気づいて適切な声がけをする

(30代女性、妊娠後期の声)「ホルモンのせいでイライラしても、『なんでそんな気分なの?』と責められた。話を聞いて共感してほしかっただけなのに。」
妊娠中の不安定な感情を理解し、ただ話を聞いてくれるだけでよかったのに、夫の反応が冷たかったり論理的すぎたりして、寂しさを感じたという声があります。
(20代女性、妊娠中期の声)「妊娠中って不安だから、もっと『大丈夫だよ』とか『いつも頑張ってるね』って言葉をかけてほしかった。」
さりげない励ましや感謝の言葉、ちょっとしたサプライズが欲しかったのに、夫が淡々としていたという不満もよく聞きます。
妻の体調変化に気づいて適切にサポートするコツは、日々の「小さな変化」を見逃さず、気配りとコミュニケーションを重ねることが大切です。
具体的には下記のポイントが役立ちます。
- 毎日「調子どう?」と声をかける
日によって体調や気分が大きく変わりやすいので、「今日の体調どう?」と、さりげなく毎日尋ねることが、変化に気づく第一歩です。 - 表情・動き・食欲の変化を観察する
顔色や口数、動作の鈍さ、横になる回数、食事のペースや好みの変化(たとえば匂いへの敏感さや食事量の増減など)を日常的に気にかけてみましょう。 - 自身の思い込みを捨てる
「昨日は元気だったから今日も大丈夫」のような推測はせず、その都度、体調や気分が違うことを前提に接するのが大切です。 - 小さな変化を言葉で伝える
「最近疲れている?」など、気付いたことをやさしく声に出して伝えると、妻も相談しやすくなります。 - 感謝や労いを言葉で積極的に伝える
「がんばってくれてありがとう」「いつもありがとう」など、感謝や労いを言葉で積極的に伝えると、自分の頑張りを認めてもらえたと感じ、精神的な安定につながります。 - 自分から手助けや家事を申し出る
何か気になる様子があれば「座っていていいよ」「今日は重いものは自分が持つね」など、具体的に負担を減らしましょう。
妊娠中の最大の不安は「ひとりで抱え込んでしまう」こと。まずは毎日「調子どう?」「何かあった?」など、積極的に声をかけ、妻の気持ちを否定せず受け止めましょう。
実践的なサポート方法
- 話をしっかり聞く・共感を示す
体調も心も揺れやすい時期なので、「無理しないで」「つらい時は言ってね」といった共感を持った言葉をかけ、決して否定しないようにします。妻の気持ちや不安を否定せず、最後まで聞いて受け止めることが最も効果的です。論理的なアドバイスや解決策よりも、「大変だったね」「つらいよね」と共感の言葉をかけることが、安心感につながります。 - 精神的サポートを大切にする
「応援してるよ」「がんばりすぎないで」と寄り添う姿勢が、実際に一番うれしかったという声が多いです。 - 妊娠に関する知識を共有する
妊娠中の体や気分の変化について勉強し、「どうしてこうなるのか」理由を理解していると、妻の変化にも気づきやすくなります。 - 転倒や無理な動作に注意
めまいやふらつきも起きやすいので、外出時は手をつないだり、重い荷物を持つなどして安全面にも配慮しましょう。
妊娠中の体調や心の変化には個人差が大きいので、「日々のささいな変化に気づく努力」と「積極的な声かけ・家事参加・共感」が、迷ったときの基本のサポートとなります。また、気になる点があれば無理をさせず、医師にも相談できる安心な環境づくりを心がけましょう。
体調変化に気づいたら、次のように声をかけるのが良い
体調変化に気づいたときの声かけは、妻を思いやる気持ちと、状況に応じた具体性が大切です。以下のような方法が推奨されます。
- 「最近、疲れてる?」や「今日は体調どう?」と、やさしく具体的に尋ねる。
- 体調を気遣う気持ちを込めて「無理しないでね」「つらかったらすぐ言ってね」と伝える。
- 「ちょっと休んだほうがいいかもね」と負担を減らす行動(休憩や座ること)を勧める。
- 気になる変化があれば「顔色がいつもと違うみたいだけど大丈夫?」など、観察した事実をやさしく言葉にする。
- すぐに手助けを申し出て「何か手伝えることある?」「これ自分がやるから座ってていいよ」と提案する。
- 気持ちを受け止める姿勢として「大変なときは遠慮なく言って」「がんばりすぎないで」と共感や理解を示す。
こうした声かけは、「否定しない」ことと「押しつけにならない」ことも重要です。妻の返答をよく聞き、本人の希望や状態を尊重しましょう。また、日々の些細な変化も気がねなく相談できる雰囲気づくりが、安心感や信頼につながります。
神対応3.妻のつわりや体調不良に対してサポートする
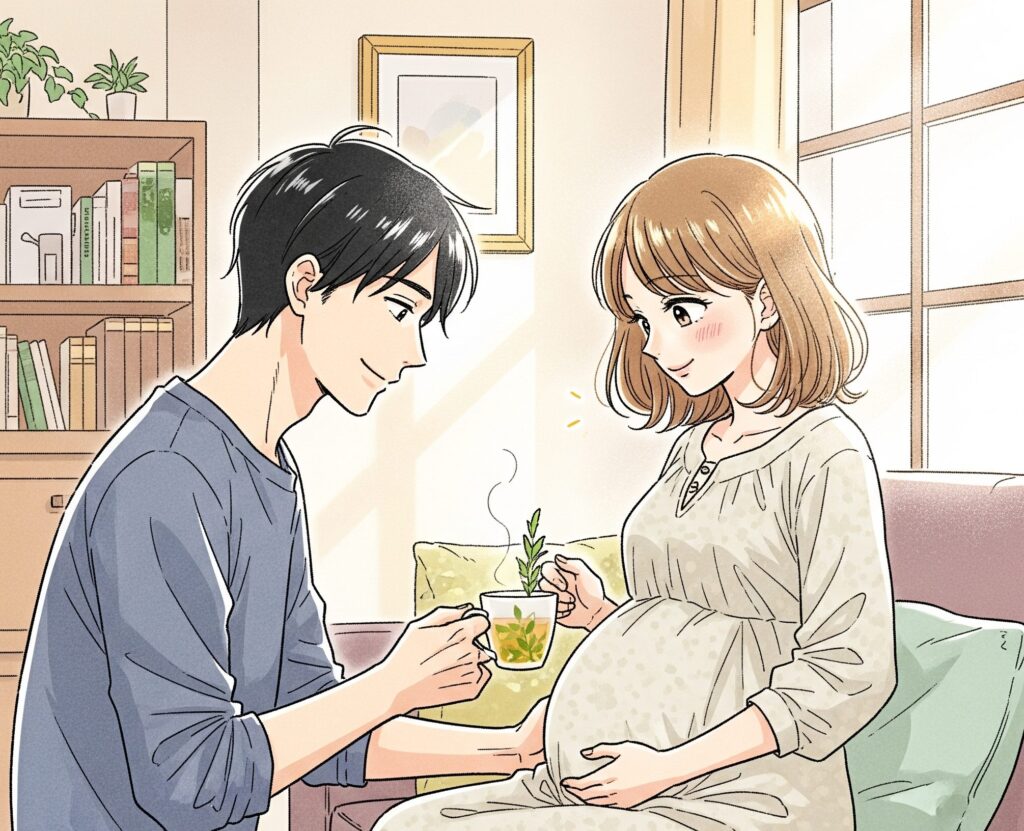
(30代女性、妊娠初期の声) 「つわりで食べられるものが限られてたのに、好きなラーメンとか匂いの強いものを家で食べられて辛かった。気遣ってほしかった。」
食事の好みや匂いに敏感になる時期に、夫が無頓着だったり、自分の好きなものを優先してしまったケースが目立ちます。
妻のつわりや体調不良に対してできる具体的なサポートは、日々の小さな負担を軽減する行動と、気持ちに寄り添う対応を組み合わせることが重要です。
つわり・体調不良への具体的サポート例
- 無理に食べさせず、体調や好みに合わせた食事を用意する
匂いや味に敏感になるので、さっぱりしたものや妻が食べやすいと感じるものを選びます。できない日はデリバリーやレトルトなども無理せず活用しましょう。 - 家事や買い物を率先して担当する
つわりがひどい時や体調がすぐれない日は、料理や掃除、洗濯、ごみ捨てなどの日常作業を夫が積極的に担います。 - 「休んでいていいよ」としっかり休息する時間を確保する
「今日は横になってていいよ」「自分がやっておくから大丈夫」と声をかけ、安心して休めるように気遣います。 - 水分や軽食をこまめに用意する
水分補給や、気分が悪い時でも食べやすい果物・ゼリー・クラッカーなどを近くに置いておきます。 - ニオイ対策を心がける
料理のにおいが気になる場合は換気や別室で調理し、タバコや整髪料、柔軟剤などもできる範囲で減らします。 - 「無理しないでね」と伝え、仕事や外出も状況を尊重する
妻自身が「できない」「つらい」と言いやすい雰囲気をつくりましょう。 - 体調の小さな変化にも気づく
顔色やしぐさ、横になる回数などを気にかけて、「しんどそうならすぐ休んで」などと声をかけます。 - 定期的に「何かできることある?」と確認する
具体的なお願い事が言いにくい場合があるため、こちらから声をかけて選択肢を示すのが有効です。 - 病院への付き添いや相談も行う
状態が心配なときは「一緒に病院へ行こうか」と提案したり、医師のアドバイスも積極的に聞くと安心です。 - 精神的サポートも怠らない
つわりや体調不良は精神的にもつらくなりやすいので、「大丈夫だよ」「一緒に乗り越えよう」と共感や励ましの声かけを心がけます。
これらのサポートは、妻が安心して妊娠生活を過ごせる環境づくりにつながります。無理をさせず、細やかな配慮とコミュニケーションで支えることが大切です。
🔻つわりついて知っておくと良いですよ♪旦那さんが協力できることがあります。
つわりが酷くて食事ができないときのママさんの味方、ベルタ葉酸サプリです♪売上No.1の葉酸サプリというだけでなく、産婦人科が推奨する葉酸サプリNo.1、葉酸サプリ口コミNo.1、妊活・妊娠中のサポートNo.1などに選出されています。

神対応4.妊娠中の感染症対策を徹底する

妊娠中の感染症対策で夫が気をつけるべきポイントは、妊婦の免疫力が低下しているため、家庭内に感染症を持ち込まないことが最重要です。具体的には以下の点に注意してください。
- 手洗い・うがい・マスクの徹底
外出先や職場から帰宅したら必ず手洗いうがいを行い、必要に応じてマスクを着用してウイルスの飛沫感染を防ぎます。 - 予防接種の確認と受けること
夫自身が風疹などの抗体がない場合は妊娠前か早めに予防接種を受けて免疫をつけることが重要です。妊婦は多くの予防接種を受けられないため、夫が予防接種を受けることで家族を守ります。 - 人混みをなるべく避けること
感染リスクの高い人混みや流行中の場所への外出を控え、外から感染症を持ち込まないようにします。 - 体調管理と休養
疲労や風邪症状がある場合は無理せず休み、家族に感染を広げない配慮をしましょう。 - 食事の衛生管理
生肉・生魚・生卵の摂取を控え、十分に加熱された料理を用意し、食中毒のリスク低減に努めること。 - 家庭内の衛生管理
ドアノブや共有物の消毒、換気をこまめに行うことも効果的です。
これらの対策を夫が積極的に行うことで、妊娠中の妻とお腹の赤ちゃんの感染症リスクを大幅に減らせます。特に風疹やトキソプラズマ胎児に影響を及ぼす感染症の予防が重要です。夫婦で情報を共有し、健康管理と感染症予防に努めましょう。
神対応5.禁煙・禁酒に協力する
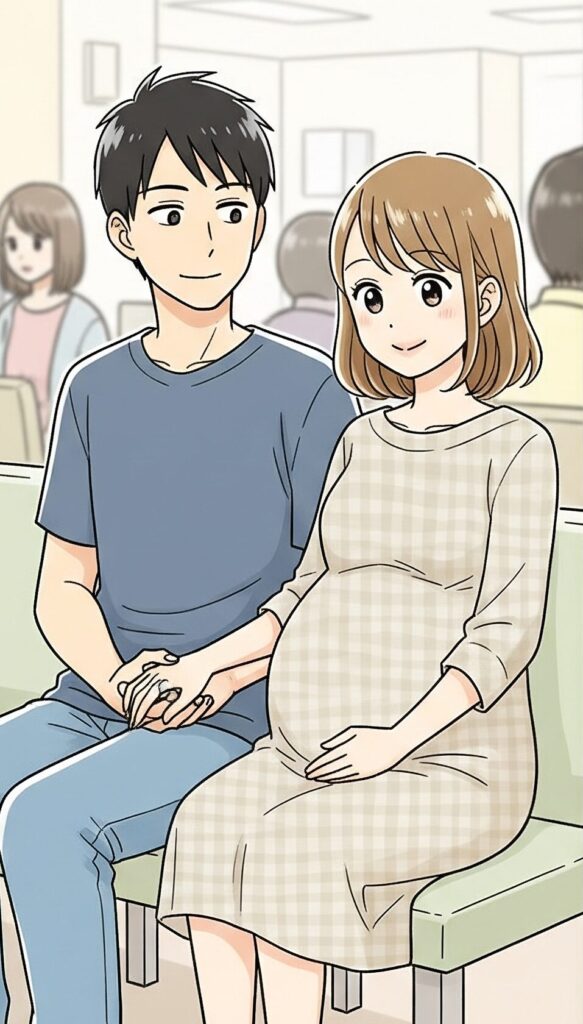
妊娠中に旦那さんが禁煙・禁酒に積極的に協力することは、妻と赤ちゃんの健康・心理にとって非常に重要です。具体的な理由と方法、生活の中での配慮ポイントをまとめます。
夫の喫煙や飲酒が妻や赤ちゃんに悪影響を及ぼすため、生活習慣の見直しを徹底しましょう。
- 受動喫煙のリスク回避
たばこの煙(副流煙)は、妊婦さん本人が吸わなくても赤ちゃんに悪影響(発育障害、流産や早産リスクの増加)が及びます。衣服や髪に残るにおいでも妻のつわりを悪化させてしまうことがあります。 - 「一人だけ我慢」のストレスを減らす
妻が禁酒中に夫だけが飲酒するのは、「自分だけ我慢しなければいけない」という心理的負担になります。夫も禁酒して連帯感を持たせ、「一緒に頑張ろう」という雰囲気づくりが大切です。 - 非常時の対応・安全面
妊娠中は予測できない体調変化や緊急事態が発生することがあります。夫が飲酒していない状態なら、すぐに運転やサポートができ安心です。 - 家の中を完全禁煙・禁酒空間にする
「換気扇の前ならOK」などはNG。家全体を禁煙禁酒エリアにし、においや副流煙が残らない環境を心がける。 - 夫婦で「赤ちゃんのため」という意識を共有
「あなたの健康のため」だけでなく、「赤ちゃんを守るために一緒に頑張ろう」と冷静に話し合い、協力をお願いする。 - 禁煙・禁酒のための外来やグッズの活用
どうしても自力でやめられない場合は、禁煙外来やノンアルコール飲料・ガムなどのサポートアイテム、病院の専門相談を利用する。 - 周囲の協力も活用
親や友人にも協力を頼み、一緒に励まし合ったり、夫だけでなく家庭全体で禁煙・禁酒ムードを高める。 - お祝いのタイミングを工夫する
「無事に出産したら一緒に乾杯しよう」など、禁酒・禁煙にゴールを設け、夫婦のモチベーションを保つ工夫も有効。
妊娠中に旦那さんがお腹の赤ちゃんに話しかけることは、家族の絆を深めたり、妻への安心感につながる大切な行動です。以下のポイントを参考に実践してみてください。
神対応6.お腹の赤ちゃんへの話しかけ

胎児は5~6ヶ月ごろから外の音を感じています。「おはよう」「おやすみ」の短い言葉でも、夫の低く響く声で語りかけることが、家族の絆やパパ自身の実感・愛情アップにつながります。
「自分から気づいて、自発的に動く」姿勢が最も妻を安心させる神対応です。
- パパ自身の父親意識が高まる
妊娠中は母親ばかりでなく、パパも赤ちゃんの存在を実感しやすくなり、育児への参加意識が芽生えます。 - 赤ちゃんの発達・情緒安定につながる
胎児は妊娠5~6ヶ月頃から音や声を感じ取ると言われ、特にパパの声は低く響きやすいので、やさしい声での語りかけが効果的です。 - 妻への心理的サポートになる
「二人で赤ちゃんを迎える」という実感が強まり、パパの思いやりや協力を感じられるので、妊娠中の安心感や信頼につながります。
実践のコツ・アイディア
- お腹に手を当てて「おはよう」「パパだよ」など、日々の挨拶や簡単な声かけをする
- ママと一緒に絵本の読み聞かせや好きな歌を歌うのもおすすめ
- 仕事帰りや寝る前など、毎日決まったタイミングで声をかけると習慣化しやすい
- 「会えるのを楽しみにしてるよ」「元気に大きくなってね」と未来を想像した前向きな言葉をかける
注意点
- 最初は照れくさいかもしれませんが、無理に長く話さず短くても継続が大切です。
- ママの体調や気分を気づかいつつ、二人でリラックスできる時間に行いましょう。
お腹の赤ちゃんへの話しかけは、妊娠中から始まる家族の絆づくりそのものです。パパの声は赤ちゃんにもちゃんと届いているので、できる範囲で毎日続けてみてください。
神対応7.妊婦健診や両親学級への付き添い
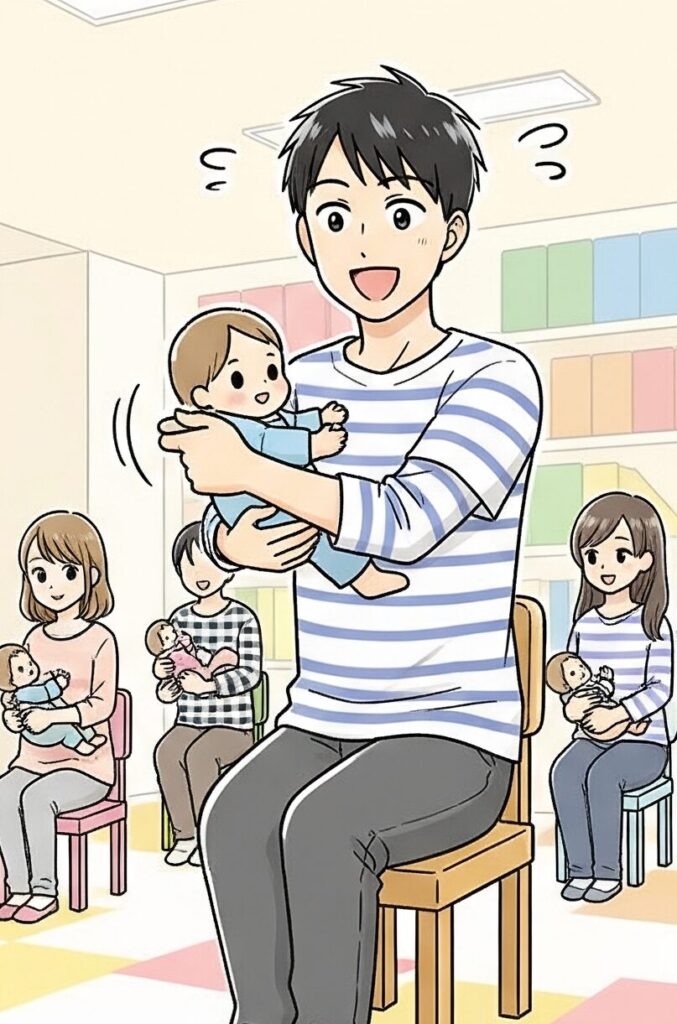
(20代女性、妊娠中期の声)「検診に一度も来てくれなかった。忙しいのはわかるけど、赤ちゃんのエコー写真を一緒に見て喜んでほしかった。」
仕事の都合などで難しい場合もあるものの、検診に一緒に来てくれることで、夫婦で赤ちゃんの成長を共有したかったという意見が多いです。
妊婦健診や両親学級への旦那さんの付き添いは、妻・赤ちゃん・家族全体にとって数多くのメリットがあります。具体的なポイントをまとめます。
妊婦健診への付き添い
- 体調へのフォローができる
妊娠中はつわりや体調不良で外出がつらいことも少なくありません。旦那さんが付き添うことで、移動時や受診の際にすぐフォローでき安心感につながります。 - 医師の説明を一緒に聞ける
妊婦健診では赤ちゃんの成長や注意点について医師から説明があります。旦那さんが同席し直接話を聞くことで、家族で情報を共有でき、適切なサポートもしやすくなります。 - 父親になる自覚が芽生えやすい
エコーで赤ちゃんの姿や心拍を見たり声を聞くことで、現実感が増し「父親になる実感」が強まったとの声が多く、積極的な育児参加や準備にもよい影響があります。 - 妊娠中の体調変化・気持ちへの理解が深まる
共に健診を受けることで、ママの心身の変化や大変さを実感でき、日常生活での気遣いやサポートがより的確になると言われています。 - ※病院によっては付き添い人数制限や男性の診察室入室不可の場合もあるため、事前の確認が必要です。
両親学級への参加
- 出産・育児の知識を夫婦で学べる
両親学級では妊娠中や出産、育児に関する基礎知識や実技(おむつ替え・沐浴・抱っこなど)を実践的に学べます。 - 父親も妊娠・出産への実感が湧きやすくなる
パートナーとして出産や育児を「自分ごと」としてとらえやすくなり、産後も含めた家事・育児への主体的な参加意識が高まります。 - 妻の不安を和らげ、家族で準備できる
未知の出産・育児に向け不安の多いママへの心の支えになり、ふたりで新しい命を迎える準備を一緒に進めるきっかけになります。 - 正しい知識でサポート力アップ
専門家から直接、妊娠中のリスクや注意点、サポート方法を学ぶことで、夫婦間の誤解や戸惑いが減り、適切な対応がしやすくなります。
実践アドバイス
旦那さんのこうした積極的な姿勢は「夫婦の絆」「父親の自覚」「ママの安心感」に直結します。家族で妊娠・出産を迎える大切な準備として、ぜひ協力しましょう。
まとめ

夫の「神対応」と呼ばれる最も効果的な具体的行動は、「気づき」+「自発的な行動」を軸に、妻の妊娠期を心と体の両面で全力サポートすることです。
男性には気づきにくいことだらけだと思いますが、ぜひこの記事で読んだことを奥さんへ実践して上げてください。
旦那さん自身も、自分のこととしてお子さんが生まれることへの喜びが増しますよ。



